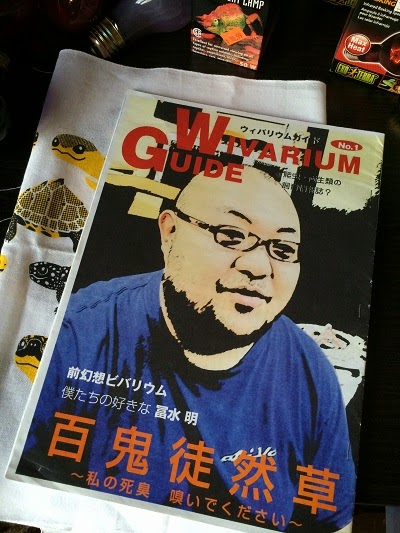Thamnophis sirtalis sirtalis
ご無沙汰しております。北バージニアより今日とれたてのイースタンガーターヘビの写真をば(クリックで少し大きくなります)。例の如く、写真では見にくいですがこれ、個人的にガーターの一番好きな体色の傾向です。こうして外で春先の複雑な光を受けていると、「蛍光グリーン」というか、もうそれ自体が発光してるんではないかと思うくらい綺麗に見えるのですけどね~・・・、家に持って帰って飼育ケースなどに入れるとただの「色褪せた黄色っぽいガーター」になってしまって、籠に入れたら茶色くなってしまうあの童話の「青い鳥」に出てくる鳥を彷彿とさせます。
この場所ではほかに姿は見えないものの、ピッカレルガエル(Lithobates palustris-ヒョウガエルに似てる中型のけっこうきれいなカエル)の、耳を澄まさないと聞こえないワビサビ系のコールも少し聞こえてきて感動した半面、期待していた水辺のサラマンダーはただの1匹も見つけることが出来ませんでした。こういうことがあると、何らかの理由で湧き水の量が減ってしまったのではないか?とか、どこかの家の庭から化学肥料が流れ込んで水質が変わってしまったのではないか?とかすぐ悪い方に考えて人生に絶望してしまうので(笑)、また出来たら若干気候条件の違う日に再挑戦して、何か収穫があることに期待したいと思います。
さて体重12キロ近くにまで成長した恐竜を体にくくりつけてフィールドグッズをしょって、寒い中大汗をかきながらなぜにこうして歩き回っていたかというと、今自宅で作成している文章にどうしても付け足したい写真を撮りに行っていたのでした。恐竜は生後1年半を迎えますます活発で、最近は微妙に人間の言葉を発するようになってきており、管理人が藪に手を突っ込んだり倒木をひっくり返したりする度に「いた!いた!」とか、「でかい!」等と(対象のいきものがいるかどうかとは関係なく)自分の口真似をしてくるので、なかなか生き物探しに集中することが出来ません。そんな状況にも負けず一生懸命したためている文章ですが、そのうちどこかでお披露目出来るかもしれませんので、その場合はまたこちらにて告知させていただけたらと思います。















%2B2.JPG)
.JPG)